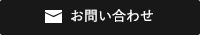2016年7月東京のホテルにて
〜第1回より続き〜
【野村】よく〝星の下で生まれる〟とかいうが、自分のこの80年間を振り返ると貧乏性・苦労性、こういう星の下で生まれてるね。その代表的なのが、プロ野球4球団の監督をやったけれど全部最下位をとったことだよ。
…と、静かに野村さんは語り始めた。
こんなことを言ったら、怒られてしまうかも知れないが、野村さんは、王さんや長嶋さんとも比較されることも多いが、生まれ持ったスター性というものを持っているのが王・長嶋だとしたら、その辺に捨てられていた石ころが、星になったというのが野村さんではないだろうか?
野村監督の魅力は、弱小球団を強くしていき最後には優勝させてしまうという、漫画の様なストーリーに魅力を感じるのは私だけではないのではないかと思う。
私は、数々の弱小球団が最終回には優勝するという、野球のドラマを見てきた一人である。
『野村再生工場』
【野村】南海・ヤクルト・阪神・楽天、それで野村再生工場とかよく肩書をつけられたけど、やっぱり上に立っている人の言う事は聞かないといけないよ。
この4球団で、俺の話を一番聞かなかったのは阪神。
─話を聞いてくれなかったのは選手ですか?
【野村】オーナーだよ。社長なんて野球の素人じゃん。こっちがああしてくれ、こうしてくれって注文出すじゃん。その手っ取り早い話がドラフト会議だよ。
野球は0点で抑えれば、100%負けないっていう当たり前の原理がそこにあるわけだよ。
0点に抑える主役はピッチャーだよ。だから投手陣から補給しましょう、というのに一つも言う事を聞かない。当時の阪神には、即戦力のピッチャーが必要なんだよ。
『株主と雇われ社長』
阪神の社長は、中小企業でいうところの出資者のような存在であり、オーナーである。野村監督はそこではいわば雇われ社長である。
当時、弱小球団と言われた阪神タイガース。企業で言えば倒産の危機である。そこで白羽の矢が立ったのが、名将で知られた野村監督だ。実績も経験も申し分ない。
ソフトバンクやベネッセ等、よく知られる大手企業でも経営不振になると外様の経営者を連れてくる。
大手でなくても、身近な話でいえば後継ぎがいないということがある。すると、トップが引退しようと思う時には、当然、他から実力のある経営者を連れてくることになる。
日産のカルロス・ゴーンのようにうまくいく会社もあれば、数年で社長の首が付けかわる会社もある。その違いはどこにあるのだろうか?
【野村】あれでは、阪神はいつまで経ってもダメだな。
野村さんが低い声でポツリとつぶやいた。
まず、阪神タイガースの場合である。
『我々の持っている、投手や野手といった戦うための戦力や指導方法、社風は間違っていないのだ。ただ指揮を振るう大将が不甲斐なかったから負けたんだ。だから監督を変えよう』という判断で連れてこられたのが、外様の野村監督である。
今までの練習などの風土は間違っていなかったんだ、というのが阪神の主張である。
それに対して、新しく戦う選手も変えて入れなおしたい。風土もやり方も変えたい、というのが野村監督の考えだ。
普通の企業でも創業者にはいろいろな思いがある。当然今までこれで出来てきたのだから、もうひと踏ん張りしたら、今までのやり方でもまだ通用するはずだ、という思いもある。
だが、歴史や風土を継承させるのであれば、外様ではなく生え抜きの監督をつくるべきではないだろうか?
外様の監督には、外様で培った経験と実績がある。外から見てきて身内にはわからない客観的な判断もできる。
創業者にとって、全てを譲り渡すという事は勇気がいる。
だが、外様の経営者を雇うという事は、創業者が自分の会社を客観的に見るという事である。
一番悪いのは、どっちつかずになり中途半端なまま経営を続けるという事である。
当然、一般企業であれば、新社長と創業者、船頭が2人もいれば船は前に進まない。会社が同じ方向に向かない会社は、社員の士気が無くなり根本が崩れることになるだろう。
創業の経営者は、思い入れが深い分、大塚家具のようにならないように、あらかじめ会社を客観的に見れるよう手放す心の準備をしておかなければならない。
その方がスムーズに次のステージに進む事が出来るのではないだろうか?
『外様社長と従業員』
─ヤクルト時代は、岡林選手をはじめ、ピッチャーを3人獲りましたよね。
【野村】阪神とは対照的。ヤクルトは全て俺の言う事を聞いてくれたね。
ドラフトで現場と編成で揉めたのよ。
その時の球団社長が※相馬さんっていうんだけど、この人の一言だよ。「お前らごちゃごちゃ言っていないで監督の言う通りにせぇ!」これで終わりだよ。
※相馬 和夫
(一九二七年─二〇〇五年)
のちに伝説の球団社長と言われる1人である。
日本の実業家。元ヤクルト本社取締役、元ヤクルトスワローズ(株式会社ヤクルト球団)球団社長1985年~1993年まで球団社長を務め、野村克也の監督招聘に成功し、1990年代の日本一3度、リーグ優勝4度のヤクルト黄金時代に尽力した。
M&Aや創業社長が変わる時、少なからず従業員との軋轢が生じる。
どの従業員も、新社長に対して表では頭を下げても本音では、お手並み拝見というところではないだろうか?
特に今までと経営と大きく方針や風土を変えようとするとき、会社の歴史があり、創業社長が長い時間を掛けつくり上げた会社ほど社員の気持ちを切り替えさせるのは難しい。
社員も目の前の給料が「来月から3倍になります」のような話であれば喜んで協力するかもしれないが、新しいやり方は、今までの評価対象と異なるという事であり、覚える事も増える。同じ給料で体制が変わるという事は社員にとってはストレスになる。
よって、新社長は明確に今後のビジョンの説明をすることと、早めに社員に試されている色眼鏡を覆す実績が必要となるのである。
ここでの相馬球団社長の一言は、「俺が連れてきた新社長だ。俺と思って扱えよ。」という強いメッセージだ。
この一言で、現場の向く方向は、新社長(監督)ひとつになったのである。
こうしてヤクルトの黄金時代は、新旧の体制が一体となる事で創られた。
相馬球団社長は、ドラフトの抽選において、「迷ったら駄目、最初に触ったものを引く。」と発言している。
それは球団経営においても同じことであり、「野村監督に任せる」と決めたら迷わない。この決断が従業員(選手)にも安心を与えたに違いない。
社員も社長の顔色を見て仕事をするものであるから、社長が優柔不断な会社で成功することはない。迷いのない決断が成功する会社をつくるという事を象徴したヤクルトの黄金時代だった。
逆に、トップが判断を迷うようになったら、その時は経営者としての引退の時期ではないだろうか?
1989年のオフシーズン、ヤクルトが野村克也氏に監督就任要請した際、ヤクルト本社の役員はファミリー主義を受け継いでいたためそれに全員反対したという。しかし、相馬氏は「失敗したら(成績が芳しくなかったら)自分も辞めます。」と役員の前で宣言し、説得したといわれている。
ここまで言われて、やらない新社長はいるだろうか?
相馬球団社長もまた一流の実業家であり、一流の経営者であったからこそ、ヤクルトは変わったのである。
会社を変えるのは、最後はトップの熱意である。
『現場と社長』
どんな立派な経営者も現場を3年も離れて社長室だけで仕事をしていると浦島太郎になってしまう。
特に今はネットの時代、時代の流れが速く、同じビジネスモデルが3年続かない。常にリニューアルや新しいものをつくり続け成長し続ける必要がある。
社長室にいると、社員は良い情報しか社長にあげてこない。社長に現場に出てこられてああだ、こうだ言われるのが面倒だからである。
逆に会社の事を思って社長に直訴する社員もいるが、現場の悪い話を聞きたがらない社長もいる。本音の所では、社長もうすうす現状を把握しているから、現状を直視したくないのだ。
だが、トップが現場を知ろうとしなくなったら、本当にその社長と心中してくれる社員はいるだろうか?
「どうせ社長は、現場のこと知らないでしょう…」
─阪神球団は、結局野村監督の意見と半々位、意見を聞いてくれたのですか?
半々もないね。それでまぁこんな事してたらね、阪神は絶対優勝できないっていう事でね、当時の久万オーナーに会わせてくれって面会を求めて行ったんだ。
とにかく阪神は歴代勝てないと監督ばっかり変えてる。監督を変えれば強くなるなんてそんな時代50年前に終わってますよ、と。野球もどんどん進化してるからね、その時代に合った運営をしていかないと…。
そこには、そう寂しそうに語る野村監督がいた…。
──次回に続く──
(聞き手) 住生活新聞
〜第1回より続き〜
【野村】よく〝星の下で生まれる〟とかいうが、自分のこの80年間を振り返ると貧乏性・苦労性、こういう星の下で生まれてるね。その代表的なのが、プロ野球4球団の監督をやったけれど全部最下位をとったことだよ。
…と、静かに野村さんは語り始めた。
こんなことを言ったら、怒られてしまうかも知れないが、野村さんは、王さんや長嶋さんとも比較されることも多いが、生まれ持ったスター性というものを持っているのが王・長嶋だとしたら、その辺に捨てられていた石ころが、星になったというのが野村さんではないだろうか?
野村監督の魅力は、弱小球団を強くしていき最後には優勝させてしまうという、漫画の様なストーリーに魅力を感じるのは私だけではないのではないかと思う。
私は、数々の弱小球団が最終回には優勝するという、野球のドラマを見てきた一人である。
『野村再生工場』
【野村】南海・ヤクルト・阪神・楽天、それで野村再生工場とかよく肩書をつけられたけど、やっぱり上に立っている人の言う事は聞かないといけないよ。
この4球団で、俺の話を一番聞かなかったのは阪神。
─話を聞いてくれなかったのは選手ですか?
【野村】オーナーだよ。社長なんて野球の素人じゃん。こっちがああしてくれ、こうしてくれって注文出すじゃん。その手っ取り早い話がドラフト会議だよ。
野球は0点で抑えれば、100%負けないっていう当たり前の原理がそこにあるわけだよ。
0点に抑える主役はピッチャーだよ。だから投手陣から補給しましょう、というのに一つも言う事を聞かない。当時の阪神には、即戦力のピッチャーが必要なんだよ。
『株主と雇われ社長』
阪神の社長は、中小企業でいうところの出資者のような存在であり、オーナーである。野村監督はそこではいわば雇われ社長である。
当時、弱小球団と言われた阪神タイガース。企業で言えば倒産の危機である。そこで白羽の矢が立ったのが、名将で知られた野村監督だ。実績も経験も申し分ない。
ソフトバンクやベネッセ等、よく知られる大手企業でも経営不振になると外様の経営者を連れてくる。
大手でなくても、身近な話でいえば後継ぎがいないということがある。すると、トップが引退しようと思う時には、当然、他から実力のある経営者を連れてくることになる。
日産のカルロス・ゴーンのようにうまくいく会社もあれば、数年で社長の首が付けかわる会社もある。その違いはどこにあるのだろうか?
【野村】あれでは、阪神はいつまで経ってもダメだな。
野村さんが低い声でポツリとつぶやいた。
まず、阪神タイガースの場合である。
『我々の持っている、投手や野手といった戦うための戦力や指導方法、社風は間違っていないのだ。ただ指揮を振るう大将が不甲斐なかったから負けたんだ。だから監督を変えよう』という判断で連れてこられたのが、外様の野村監督である。
今までの練習などの風土は間違っていなかったんだ、というのが阪神の主張である。
それに対して、新しく戦う選手も変えて入れなおしたい。風土もやり方も変えたい、というのが野村監督の考えだ。
普通の企業でも創業者にはいろいろな思いがある。当然今までこれで出来てきたのだから、もうひと踏ん張りしたら、今までのやり方でもまだ通用するはずだ、という思いもある。
だが、歴史や風土を継承させるのであれば、外様ではなく生え抜きの監督をつくるべきではないだろうか?
外様の監督には、外様で培った経験と実績がある。外から見てきて身内にはわからない客観的な判断もできる。
創業者にとって、全てを譲り渡すという事は勇気がいる。
だが、外様の経営者を雇うという事は、創業者が自分の会社を客観的に見るという事である。
一番悪いのは、どっちつかずになり中途半端なまま経営を続けるという事である。
当然、一般企業であれば、新社長と創業者、船頭が2人もいれば船は前に進まない。会社が同じ方向に向かない会社は、社員の士気が無くなり根本が崩れることになるだろう。
創業の経営者は、思い入れが深い分、大塚家具のようにならないように、あらかじめ会社を客観的に見れるよう手放す心の準備をしておかなければならない。
その方がスムーズに次のステージに進む事が出来るのではないだろうか?
『外様社長と従業員』
─ヤクルト時代は、岡林選手をはじめ、ピッチャーを3人獲りましたよね。
【野村】阪神とは対照的。ヤクルトは全て俺の言う事を聞いてくれたね。
ドラフトで現場と編成で揉めたのよ。
その時の球団社長が※相馬さんっていうんだけど、この人の一言だよ。「お前らごちゃごちゃ言っていないで監督の言う通りにせぇ!」これで終わりだよ。
※相馬 和夫
(一九二七年─二〇〇五年)
のちに伝説の球団社長と言われる1人である。
日本の実業家。元ヤクルト本社取締役、元ヤクルトスワローズ(株式会社ヤクルト球団)球団社長1985年~1993年まで球団社長を務め、野村克也の監督招聘に成功し、1990年代の日本一3度、リーグ優勝4度のヤクルト黄金時代に尽力した。
M&Aや創業社長が変わる時、少なからず従業員との軋轢が生じる。
どの従業員も、新社長に対して表では頭を下げても本音では、お手並み拝見というところではないだろうか?
特に今までと経営と大きく方針や風土を変えようとするとき、会社の歴史があり、創業社長が長い時間を掛けつくり上げた会社ほど社員の気持ちを切り替えさせるのは難しい。
社員も目の前の給料が「来月から3倍になります」のような話であれば喜んで協力するかもしれないが、新しいやり方は、今までの評価対象と異なるという事であり、覚える事も増える。同じ給料で体制が変わるという事は社員にとってはストレスになる。
よって、新社長は明確に今後のビジョンの説明をすることと、早めに社員に試されている色眼鏡を覆す実績が必要となるのである。
ここでの相馬球団社長の一言は、「俺が連れてきた新社長だ。俺と思って扱えよ。」という強いメッセージだ。
この一言で、現場の向く方向は、新社長(監督)ひとつになったのである。
こうしてヤクルトの黄金時代は、新旧の体制が一体となる事で創られた。
相馬球団社長は、ドラフトの抽選において、「迷ったら駄目、最初に触ったものを引く。」と発言している。
それは球団経営においても同じことであり、「野村監督に任せる」と決めたら迷わない。この決断が従業員(選手)にも安心を与えたに違いない。
社員も社長の顔色を見て仕事をするものであるから、社長が優柔不断な会社で成功することはない。迷いのない決断が成功する会社をつくるという事を象徴したヤクルトの黄金時代だった。
逆に、トップが判断を迷うようになったら、その時は経営者としての引退の時期ではないだろうか?
1989年のオフシーズン、ヤクルトが野村克也氏に監督就任要請した際、ヤクルト本社の役員はファミリー主義を受け継いでいたためそれに全員反対したという。しかし、相馬氏は「失敗したら(成績が芳しくなかったら)自分も辞めます。」と役員の前で宣言し、説得したといわれている。
ここまで言われて、やらない新社長はいるだろうか?
相馬球団社長もまた一流の実業家であり、一流の経営者であったからこそ、ヤクルトは変わったのである。
会社を変えるのは、最後はトップの熱意である。
『現場と社長』
どんな立派な経営者も現場を3年も離れて社長室だけで仕事をしていると浦島太郎になってしまう。
特に今はネットの時代、時代の流れが速く、同じビジネスモデルが3年続かない。常にリニューアルや新しいものをつくり続け成長し続ける必要がある。
社長室にいると、社員は良い情報しか社長にあげてこない。社長に現場に出てこられてああだ、こうだ言われるのが面倒だからである。
逆に会社の事を思って社長に直訴する社員もいるが、現場の悪い話を聞きたがらない社長もいる。本音の所では、社長もうすうす現状を把握しているから、現状を直視したくないのだ。
だが、トップが現場を知ろうとしなくなったら、本当にその社長と心中してくれる社員はいるだろうか?
「どうせ社長は、現場のこと知らないでしょう…」
─阪神球団は、結局野村監督の意見と半々位、意見を聞いてくれたのですか?
半々もないね。それでまぁこんな事してたらね、阪神は絶対優勝できないっていう事でね、当時の久万オーナーに会わせてくれって面会を求めて行ったんだ。
とにかく阪神は歴代勝てないと監督ばっかり変えてる。監督を変えれば強くなるなんてそんな時代50年前に終わってますよ、と。野球もどんどん進化してるからね、その時代に合った運営をしていかないと…。
そこには、そう寂しそうに語る野村監督がいた…。
──次回に続く──
野村 克也
1935年6月29日生まれ
野球解説者・評論家。元ヤクルトスワローズ、阪神タイガース、東北楽天ゴールデンイーグルス監督。元プロ野球選手(捕手)で、戦後初・捕手として世界初の三冠王を獲得。データを重視するという意味の「ID野球」(造語)の生みの親でもある。「何よりも自分は働く人間」と語っており、幼少期から80歳を過ぎた現在でも休まずに仕事に取り組む姿勢は、野球ファンのみならず、経営者にもファンが多い。
1935年6月29日生まれ
野球解説者・評論家。元ヤクルトスワローズ、阪神タイガース、東北楽天ゴールデンイーグルス監督。元プロ野球選手(捕手)で、戦後初・捕手として世界初の三冠王を獲得。データを重視するという意味の「ID野球」(造語)の生みの親でもある。「何よりも自分は働く人間」と語っており、幼少期から80歳を過ぎた現在でも休まずに仕事に取り組む姿勢は、野球ファンのみならず、経営者にもファンが多い。